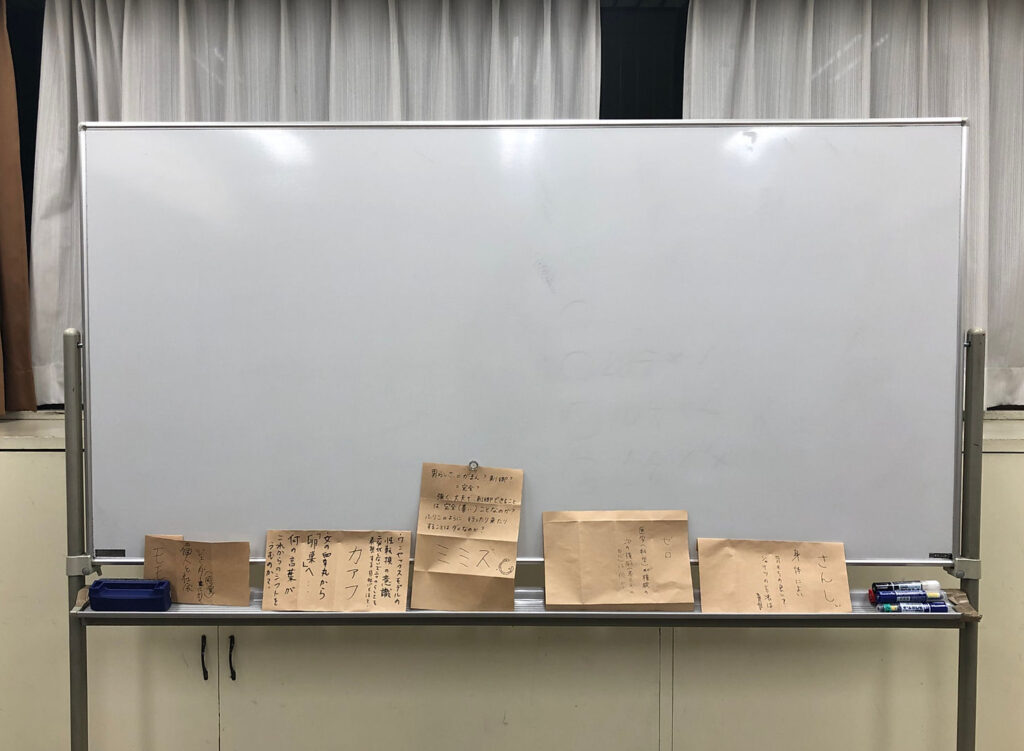
第十回
2025年5月25日 日曜日
参加者:4名
ジェンダーロールを乗り越えようの会
「身体史からみる身体イメージ」
第十回となる今回のジェンダーロール勉強会では、弓削尚子著『はじめての西洋ジェンダー史──家族史からグローバル・ヒストリーまで』の第4章 「男女の身体はどう捉えられてきたか」 ― 身体史を読み、意見交換を行いました。
解剖学が発展していく過程で変化してきた男女の身体像について学び、それぞれが受けてきた教育が、自分の身体をどうイメージすることにつながったのかについて確認する時間となりました。
解剖学と身体
解剖学が発展する前、人々は自らの身体内部を想像するしかなく、言葉によって身体感が捉えられていたようです。
「見えない部分は、言葉でできている」
13世紀から14世紀頃、解剖学が登場することで、身体理解の権威は宗教者から医者へと移っていきました。しかし、医者もすべてを見ることはできなかったため、身体の内側にある異変や症状を説明する患者の言葉を信じることで、身体のありようを理解しようとしていたようです。
当時、月経が止まった理由として「犬に吠えられたから」という患者の説明から、身体の出来事を自然現象や動物の行動に結びつけて理解しようとしていた時代背景が伺うことができます。そこには今のような医者が診る、患者が診られるという一方的な構図は、まだ存在していなかったようです。
解剖によって実際の臓器や構造が明らかになっても、人間の認識はすぐには変わりませんでした。たとえば、卵巣を女性の睾丸として理解する見方は、解剖して実際の臓器を見ることができた後も、当時の身体観によって、すぐに「卵巣」という言葉が形成されるまでには至らなかったようです。
信じる対象が宗教から科学や医学へと移っていく過程で、男女の身体はどうかわってきたのか西洋身体史を振り返り皆で確認することができました。
着衣と身体
女性は産む性、男性は戦う性という二元的な役割分担や、長い歴史の中で身体管理のあり方や服装の結びつきについて話し合いました。
「性器を守る−服装と身体観をめぐって」
近年はフェムテックの発展によって、生理との向き合い方も変化してきました。たとえば、タンポンではなく月経カップを使う人がいます。これは、膣内にカップを挿入して経血を溜めるものです。ただし、プールやお風呂で完全に安心というわけではなく、個人の身体感覚や生活スタイルに合わせて選ばれています。
「使い捨てしない下着を身につけていた昔は、洗うのが大変だから、なるべくトイレで経血を出すことができた」という話しも共有されました。同様に、「赤ちゃんの排泄リズムやサインを読み取る身体感覚を育てるオムツなしの育児法をとりいれることで、生活の手間を減らそうとするトレーニングもある」といった事例も紹介されました。
ナプキンについても、「ケミカルな素材が肌に与える影響が懸念されるなかで、オーガニックコットンや化学物質を極力含まない素材を使ったナプキンが登場し、女性の生理用品に身体に寄り添う選択肢が増えてきた」との意見が出ました。
「アクセサリーとしての性別表現」
男女の骨格を示した昔のある解剖学の図解には、男性の背景に馬の骸骨、女性の背景にはダチョウの骸骨が描かれていました。馬はコントロール可能な力強い存在として男性性の象徴として、ダチョウは羽根をまとい巨大な卵を産む存在として、女性の飾る身体や母となる身体のイメージと重ねられていたようです。
このような視覚的な象徴表現から、参加者からは「現代における性別とアクセサリーの関係」についても意見が出ました。たとえば、「インスタグラムなどで子どもをアクセサリーとしている女性が見受けられる」といった指摘や、「男性は靴にこだわる傾向がある。かつては車や腕時計だったが、今はスニーカーがステータスを示すアイテムになっている」といった声もありました。
さらに、参加者からは「アクセサリーには自己顕示だけでなく、護身目的の使い方もある。一人暮らしの女性が玄関に男性用の靴を置く、洗濯物に男性物のシャツを干すといった工夫がなされている」との具体的な事例も紹介されました。
弱い女性?強い男性?
女性は弱い性、男性は強い性——私たちはこのイメージを、どこで、どのように刷り込まれてきたのかについて話し合いました。
「弱い性という身体イメージ脱却のために」
運動の機会が少なければ、当然、筋肉量も少なくなるし、体力も落ちる。参加者からは「学校でのダンスの授業で、男性がリードし、女性は優雅に従うレディの役を担わされた」という経験談がありました。そこには身体を鍛えるというより性別役割を演じるという側面があります。しかし、農村や工場では、かつて多くの女性が男性と同じように身体を使って働いていました。つまり、弱い性というイメージは生まれ持ったものではなく、ある種の演出によってかたちづくられてきたことが話し合われました。
また、動物の世界についても意見が出ました。鳥の世界ではオスが着飾り求愛する種が多く、人間社会で「装う性」が女性とされることとの対比が挙げられました。虫の世界ではメスの方が大きく、時にはオスを食べる種もいます。一方で人間社会の男らしさや女らしさは、文化と時代、さらには階級や政治的都合によって作られ、変化していくもののようです。
参加者からは「日本の学校教育にも、性別による身体感覚の刷り込みが日常的にある」との指摘もありました。たとえば、体育祭で危険だから女子は除外するという競技の振り分けや、男子1500m・女子1000mといった距離の違いなどが挙げられました。身体をどう使い、どこまで鍛えさせるかという教育的なデザインは、国家による性別認識の影響も反映されているようです。
本来、身体はひとりひとり異なります。走ることが好きな人もいれば、好きでない人もいる。何かをさせられるよりも、自分の身体をどう使いたいかを自分で選べる自由が、性別を超えて保障される社会にしていくために、何ができるのか問われました。弱い性のイメージの問い直しは、まず私たちが自分たちの身体感覚を取り戻すことからはじめられるのかもしれません。
「男子の感情制御とオナニー」
感情を抑えること、性欲を我慢することが男性らしいとされてきた背景には、宗教的・歴史的な制御の文化があります。オナニーは生殖につながらないため体に悪いとされ、男性の性欲の制御手段として、かつては瀉血が行われていたという記録もあります。
「女性は生理を通じて自然に血を出す機会がありますが、男性の身体にはそのようなリズムがないため、制御が問題となるのかもしれない」との意見もありました。「古いものを排出して新しいものをつくるという考え方から、オナニーすることで精子を循環させる方が健康だ」という考え方も共有されましたが、昔は血を循環させるということで感情の制御を取り戻そうとしていたようです。
参加者からは「男性は感情を表に出してはいけない、泣いてはいけない」と言われてきたとの声もあり、性欲だけでなく、感情についても制御できる男性像が理想とされる傾向が指摘されました。
学校の保健体育では、生理や精通は教えても、オナニーについては触れられなかったことが参加者から指摘されました。オナニーをすると頭が悪くなる、癌になるなど子どもたちの間で話されていたようです。一方で、女性には性欲がないという思い込みも存在し、女性同士の間でも、オナニーについて語られる機会は少なかったという意見も出されました。
記録:ダンシロウ
参考文献:
「はじめての西洋ジェンダー史 家族史からグローバル・ヒストリーまで」
弓削尚子(ゆげ なおこ)著
第四章「男女の身体はどう捉えられてきたか」 ― 身体史」
西洋のジェンダー史を各分野の歴史家たちの視点から学べる入門書。ジェンダーが歴史的にどのように構築されてきたのかを理解することで、ジェンダーの脱構築を考える手がかりとなる一冊です。